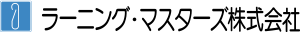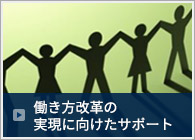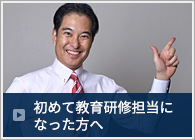エンゲージメントを生む組織を作る対話の質
人材の定着が大きな課題
 若手社員の早期離職は、多くの企業が直面する課題です。入社後3年以内の退職率は、2024年度の大学卒就職者で34.9%という厚生労働省のデータ(※)もあり、「せっかく採用した人材が定着しない」という悩みは、経営層から人事担当者、現場マネジャーに至るまで共通のものとなっています。
若手社員の早期離職は、多くの企業が直面する課題です。入社後3年以内の退職率は、2024年度の大学卒就職者で34.9%という厚生労働省のデータ(※)もあり、「せっかく採用した人材が定着しない」という悩みは、経営層から人事担当者、現場マネジャーに至るまで共通のものとなっています。
この背景の1つとして、近年特に指摘されているのが、職場内のコミュニケーションや対話の質です。企業が優秀な人材を引きつけ、育成し、長く活躍してもらうには、制度や待遇だけではなく、若手社員と関わるリーダー層の対話力や日々の会話のあり方を見直す必要があります。
[※ 参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(2021年3月卒業者)」]
離職の理由は「対話不足」
若手社員が離職を考える理由には、以下のようなものがあります。
- 仕事に対する期待や評価基準が曖昧で、適切なフィードバックや承認が得られない
- 期待や目標が明確に共有されないと、自分の成長が実感できず、やる気が低下する
- フィードバックの場が少なく、伝えられるのが突然の「評価結果」だけだと、信頼関係が構築できず、組織への帰属意識を持てない
- 組織文化に心理的安全性がなく、自分のキャリアや希望について話す場もない
- 社員一人ひとりが安心して意見や不安を話せる場がないと、不満が蓄積し、退職へとつながる
これらの根底にあるのは、上司とのコミュニケーション不足です。
難しい対話を良質な対話に
こうした状況は制度の問題でもあるため、組織は若手との1on1や、積極的に改善点を伝えるフィードバックをリーダーに推奨しますが、現場ではなかなか定着しないようです。その大きな理由に、対話の機会を増やしたとしても、リーダー自身が「難しい対話をどう進めればよいか分からない」という、対話力(対話の質)の問題があります。
難しい対話とリーダーが持つ不安の例
| 難しい対話 | リーダーが持つ不安 |
|---|---|
| 期待を明確に伝える | 高圧的になってしまうのではと心配になる |
| パフォーマンスに課題がある社員に 改善を促す |
傷つけたくなくて曖昧なメッセージになる |
| 部下のキャリア希望を聞き出す | 本音を引き出せず表面的な会話で終わる |
| 意見が異なっても建設的な議論をする | 衝突を避けるために、話題そのものを避ける |
残念ながら、多くのリーダーは、難しい対話をうまく進めるための具体的な手法を学ぶ機会がなく、対話力に不安を抱えながら現場に立っているのが現実です。
良質な対話の例
- 上司から明確に期待を伝え、日々の進捗や成果を承認している
- 部下が安心して本音を話せる環境がある
- 定期的な1on1でキャリアの希望や悩みについて話し合っている
- フィードバックの場が、評価伝達だけではなく、成長を支援する対話になっている
このような対話ができるリーダーがいる職場では、若手社員は「ここで成長できる」「自分の声が聞かれている」と実感しやすく、離職意向が大きく下がる傾向があります。対話の質が文化をつくり、文化がエンゲージメントを生む——これは国内外の多くの調査でも裏づけられています。
部下の本音を引き出す対話スキル
当社が提供する教育研修プログラム「クルーシャル・カンバセーション」では、難しい対話に必要なスキルを体系的かつ実践的に学べます。
「クルーシャル・カンバセーション」で学べるスキルの一部
- 意見が対立する場面を避けずに効果的な対話に踏み込むスキル
- 感情的な状況でも冷静に会話を進めるスキル
- 自分の意図を率直かつ相手に受け入れやすい形で伝えるスキル
- 部下の本音やキャリア希望を引き出すスキル
実際に受講された方からは、「若手との1on1が変わった」「部下との信頼関係が築けるようになった」「難しい話題も避けずに話せるようになった」といった変化の声が届いています。
9月には公開講座を開催予定です。また、気軽に内容を体験していただける無料セミナーも実施しています。若手社員の離職防止や組織文化の改善に取り組んでいる方は、まずこの機会をご活用ください。対話力の向上は、組織全体の未来を変える一歩になるはずです。
グルストーッフ トーマス
- 【2025年9月 無料セミナー】
「違い」を力に変えるダイバーシティ・コミュニケーション - 世代や考え方が違う相手と、心理的安全性が高く、誰もが働きやすい組織を作るために、日常で使える具体的な対話の手法をお伝えします。
- 【2025年9月 無料セミナー】個人と組織の健全性を高める
変革を推進し成果を最大化する重要スキル - リーダーが影響力を持って適切な行動を促し、メンバーそれぞれが対話の質を高め、効率的に仕事をし、生産性の向上を可能にします。世界中で何百万人もの人々が学ぶ、実用的なフレームワークです。