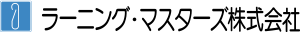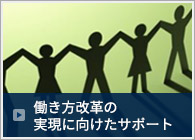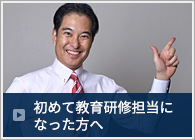ATD 2025 International Conference & Expo参加報告
 2025年5月18日~21日にアメリカ・ワシントンD.C.で開催された「ATD 2025 International Conference & Expo(ATD2025)」に参加しました。80カ国以上から教育研修や人材開発に関わる専門家が集まる世界最大級の人材開発イベントで、今回の参加者は8,400人とのことです。私は、サンディエゴで開催されたATD2023に続き、2年ぶりの参加となりました。
2025年5月18日~21日にアメリカ・ワシントンD.C.で開催された「ATD 2025 International Conference & Expo(ATD2025)」に参加しました。80カ国以上から教育研修や人材開発に関わる専門家が集まる世界最大級の人材開発イベントで、今回の参加者は8,400人とのことです。私は、サンディエゴで開催されたATD2023に続き、2年ぶりの参加となりました。
AIがもたらす変化とは
人材育成を取り巻く環境もITテクノロジーの進化に影響を受け、AIの活用をはじめ、ラーニングテクノロジーの変化に関心が高まっています。今年のATDでは、講演でも各社の展示ブースでも、AIへの関心が高く、提供される情報カテゴリーのタグ付けトップも「AI」でした。
AIの導入事例紹介や、各国でのAI活用度合いに関するパネルディスカッションなどは、どれも人気があったようです。個人的には、Creative AI Academy創設者の1人であるTony Jones氏の講演「Revolutionizing Learning: 3 Ways AI Personalizes Learning Pathways(訳:AIが学習過程をパーソナライズする3つの方法)」で、AIが業務におよぼす影響だけでなく、文化や風土におよぼす影響についても言及している点が興味深く感じました。
製品展示ブースでも、AIを取り入れたソリューションや、オンラインコーチングの紹介が目立ちました。操作性も、2年前と比較して格段に進んでおり、私のようにITに弱い人間にも扱いやすくなっています。
研修展示ブースでは、研修そのものよりも、研修後のフォローアップにAIを組み込むケースが多く見られました。AIを使った1on1練習用の状況設定も豊富で、より現場に即したシナリオが作り込まれていたり、または、ユーザーが各々で作り込めたりと、ユーザーが求める形へ進化していることが感じられます。こちらも、操作性は上がっています。
もう1つ興味深かったのは、提供される研修の変化です。例えば、従来のリーダーシップ研修のスタンダードは「2日間の研修と、フォローアップ」という形式でした。しかし、これを「ラーニング・ジャーニー」とシリーズ化して、受講者が経験を重ねながらさらに長い期間をかけて学び、そこにAIを使ったフォローも組み込む、といった解決策を提供しているブースが増えている傾向が印象的でした。
技術の変化が意識の変化をもたらす
 そうした状況もあり、参加する講演は各種情報カテゴリーから「Future Readiness(訳:未来への準備、変化対応)」を中心に選択しました。なかでも印象に残ったのは、Dr. Selina Neri氏の「Future Readiness: Developing Future-Ready Talent(訳:未来に対応できる人材の育成)」です。
そうした状況もあり、参加する講演は各種情報カテゴリーから「Future Readiness(訳:未来への準備、変化対応)」を中心に選択しました。なかでも印象に残ったのは、Dr. Selina Neri氏の「Future Readiness: Developing Future-Ready Talent(訳:未来に対応できる人材の育成)」です。
講演では、AIの活用が進むことで業務が効率化され、これまでの業務がなくなると同時に業務プロセスに変化が起こり、人材育成にも影響をおよぼすという話がありました。
以下は、実際に講演で挙げられていた変化の例です。
| やめること | 新たに始めること |
|---|---|
| 先輩が後輩を指導するメンタリング | 後輩が先輩を指導するメンタリング |
これまでの指導とは、先輩が時間と経験によって得たものを、後輩に伝承することでした。「先輩の経験」が価値を生み出し、メンタリングによって、その「価値」も経験が多い人から少ない人に伝承されていました。
技術が進化し、先輩の培ったものが言語化され、経験を得た当人が経験の伝承を行う必要はなくなる可能性があります。「将来的に現在の仕事はなくなるだろう」といったことは、すでに多く語られていますが、Neri氏は、「価値」そのものにも変化があり、経験が少ない人が持っている何かが、価値を生むようになる、そして、その新たな価値あるものを、経験が多い人に伝承するようになることが考えられると言います。
これらは、ただ「技術の進化で仕事の進め方が変わる」ということだけでなく、「経験者から教わる」「経験者だから教えられる」「時間で得た経験に価値がある」という私たちのパラダイム(固定観念)を変えないと、組織として「価値」を生み続けることができなくなる未来を示しています。技術やプロセスの変化は、同時に私たちの考え方、固定観念も問われることになります。
未来へ備えるために
今後は国内でもさまざまな場面でAIがさらに普及、浸透することが予見できます。こうした変化に、日常の業務や人材開発の機会提供など、私たちのお客さまだけでなく、私たち自身もどのように対応していくのかが、今後の大きな課題です。
Neri氏の講演の中で、未来学者であるアルビン・トフラーの名前も出てきましたが、私たちは今、まさにトフラーの言う「未来」に直面していると言えるでしょう。「パラダイムを変える」、これは、トフラーの言う「未来」に対する備えとして重要な点です。
トフラーの有名な言葉の1つ「将来の文盲とは、読み書きのできない人ではなく、学ぶことも、学んだことを捨てることも、また学び直すこともできない人のことである」を繰り返し思い起こし、「いかに学ぶか」を問い続けなければいけない。そうあらためて感じるATD2025でした。