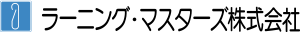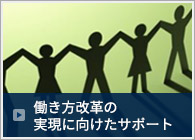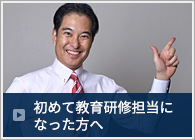「思い込まない」情報の扱い方 第2回
繰り返す情報のインプットとアウトプット
 以前のコラムで、人の思い込みや決めつけについて述べました。今回は、人の認知について、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
以前のコラムで、人の思い込みや決めつけについて述べました。今回は、人の認知について、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
私たちは、日常的に情報のインプットとアウトプットを繰り返しています。聞く(in)、話す(out)、読む(in)、書く(out)、見る(in)、思い出す(out)。認知心理学においては、こうした日常的な活動の中に、「思い込み」や「決めつけ」の原因が存在すると考えられています。
人が新しい情報をインプットする際には、情報をそのまま覚えるのではなく、自分が覚えやすいように解釈を加えて記憶すると言われています。例えば、「これはあれと近い」や「この人はいつもこうだな」などです。すでに頭の中にある情報と関連づけた方が、情報を1つずつ独立させるより、たくさん、かつスムーズに記憶できるからです。
アウトプットの際には、インプット時の解釈を頼りに、情報の復元を試みます。つまり、元の情報をそのまま取り出すわけではありません。ここで、元の情報からずれてしまうことがあります。
さらに厄介なことに、私たちは、自分がアウトプットした情報を、同時にインプットしています。このようなプロセスを繰り返すことで、伝言ゲームのように、元の情報とかけ離れた情報になってしまう。これが「思い込み」や「決めつけ」の原因であるそうです。
思い込み、決めつけとは
重要なのは、人がはじめから情報を「歪めて認知しよう」と思っているわけではない、ということです。純粋に「自分にとって自然であり、理解しやすい」と無意識に判断し、自然に繰り返した結果、認知を歪めてしまうわけです。
代表的な「思い込み」や「決めつけ」には、次のようなものがあります。
| 認知的不協和 | 自分に都合の良いことを積極的に取り入れ、都合の悪いことは見ようとしない |
|---|---|
| 総意誤認効果 | 情報を自分の考えに寄せて推測する |
| 素朴理論 | 過度の一般化や、飛躍した帰納的推論をする |
仕事や人づき合いにおいて、情報の共有は重要です。さらには、「情報をどのように解釈するか」まで共有できると、非常にスムーズなやりとりが行えるでしょう。
しかし、現実はどうでしょうか。「上司と話がかみ合わない」「お客さまの発言の意図を取り違えてしまう」「よかれと思ってやったことを快く受け止めてもらえなかった」…。解釈の共有がいかに大変か、皆さんもさまざまな経験で感じていると思います。
では、どうすれば認知の歪みを防ぐことができるのでしょうか。またの機会に、そうしたことについて考えてみたいと思います。