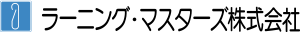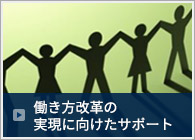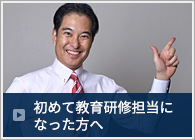相手にとって居心地が良い対応のために
職場の「空気」への関心
 社会は変化し続けていますが、いわゆる「空気を読める/読めない」ことへの関心の高さは、変わらないように思います。私が研修講師として関わる各企業の新入社員からは、今年も「職場で気がつく人になりたい」という感想が多くありました。また、先日目にしたデータでも、新入社員や若手社員が得意なこととして「相手基準での行動」「協働」が上位を占めていました。
社会は変化し続けていますが、いわゆる「空気を読める/読めない」ことへの関心の高さは、変わらないように思います。私が研修講師として関わる各企業の新入社員からは、今年も「職場で気がつく人になりたい」という感想が多くありました。また、先日目にしたデータでも、新入社員や若手社員が得意なこととして「相手基準での行動」「協働」が上位を占めていました。
ビジネスにおいて、あえて「空気を読まない」選択が変化や変革につながることもありますが、その場合も、「空気」を察してはいるわけです。多様性が尊重され、社会の変化から企業の組織体制や風土も変わり、上意下達が絶対ではなくなってきたからこそ、年代に関わらず、多くのビジネスパーソンが「空気を読む」「職場で気がつく」ことに関心を寄せるのかもしれません。
気遣いではなく気づく人
これは私の学生時代の話なので、現在では肯定や共感が難しいかもしれませんが、当時、部活の監督から繰り返し言われていたのは、「気を遣うな、気づけ!」でした。現在の私なりに言葉にすると、『気を遣われるのは居心地が悪いが、気づいてくれる人といるのは心地よい』ということでしょう。
監督をさりげなく観察し、何をしようとしているか、何をしてほしいのかに気づき、そして自分が何をすべきか考え、行動までのすべてが自然の流れ、当たり前の雰囲気で行われることが重要でした。いつもどおりにしたつもりでも、監督の思いとは違っていたり、「ここぞ」というタイミングを外したり…。そんなときは、とにかく考えるしかありませんでした。
双方向で心理的安全性を確立する
現代の職場では、一方向に気を遣うコミュニケーションではなく、お互いを受容し、双方向で心理的安全性を確立していくことが重要な課題です。時代は変わっても、自分と相手が共有する時間が、相手にとって居心地が良いものであるかどうかが重要なのは、変わらないはずです。
- 情報共有や報・連・相において、「気がつく人」になっているか
- リアクションやフィードバックが、「ここぞ」を外していないか
- 日々の声かけは、「自然の流れ」でできているか
- (逆の立場で)気づいてもらえる情報をうまく提供できているか
コミュニケーションに「正解」はありませんが、すべてのコミュニケーションに外せない「ここぞ」があるのではないでしょうか。こういった内省から導き出した課題に対して、例えば、当社の教育研修プログラムと診断ツールでは以下のようなお手伝いができます。
相手の受容につながる率直な伝え方
- 反対意見がある
- 重要な結果を伴う
- 強い感情にとらわれる
これら3つの要素が含まれる重要な会話の場面で、自分と相手が望む結果を導くために、会話をうまく進めるスキルを学びます。話すのをためらって先延ばししてしまうような内容でも、タイミングを逃さずに意義のある対話に踏み出せるようになります。意見の相違を対話に変え、前向きな対話を促進する実践的なスキルです。
相手にとっての「居心地の良さ」を知る
人にはそれぞれ、うまく付き合える相手と、うまく付き合うのがむずかしい相手がいます。パーソナル・スタイルに基づいて、相手にとって居心地の良いコミュニケーションを知り、それに合わせた言動を選ぶスキルを学ぶことで、双方が満足できる人間関係を目指したコミュニケーションができるようになります。
相互理解、違いを知る
人の行動の基になっている「パーソナリティ」を診断し、自己理解を高めます。職場で必要とされる行動が、自分にとって自然にできることか、または苦労を要するかが分かるため、他者への影響力を発揮すべき場面で、何ができるかだけでなく、どれだけ努力すればいいかが明確になります。自分を知るだけでなく、チームメンバーごとの傾向が一覧化されたチーム向けレポートもあります。
営業から学ぶ「相手基準」
「これは良い商品なので、買ってください」のような営業は、自分本位と言えます。では、相手の立場に立った営業とは、どういうものでしょうか。お客さまとの信頼関係をベースに、「的確なニーズ把握」や「問題解決の提案」などのスキルを習得できます。営業活動のみならず、さまざまな職種での業務上のコミュニケーションにも役立つと、多くの受講者からご好評をいただいている研修プログラムです。
9月に開催する無料セミナーでは、「「違い」を力に変えるダイバーシティ・コミュニケーション」をテーマに、考え方が違う相手と、違いを受け入れるだけではなく、違いを活かすコミュニケーションスキルを紹介します。想定と異なる状況で、「なぜこの人はこうしたのだろう」と考え直す力や、自分の考えをうまく言葉にする力の養い方など、日常で使える具体的な対話の手法です。ぜひご参加ください。
- 【2025年9月 無料セミナー】「違い」を力に変えるダイバーシティ・コミュニケーション
- 心理的安全性が高く、誰もが働きやすい組織を作るために、相手の気持ちや考えを引き出す問いかけや、自分の気持ちの率直な伝え方など、日常で使える具体的な対話の手法をお伝えします。