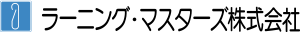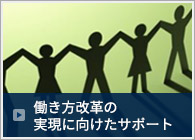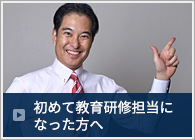新入社員や若手社員の「主体性がある」とは
気になることを「把握する」、行動と目的を「見極める」
 企業の新人採用における人材要件として、「主体性があること」や「自分で考え自分で動けること」がよく挙げられます。一方で、それが自分で考えたことであっても、「自分勝手」に動き始めると、組織としては困った状態になります。
企業の新人採用における人材要件として、「主体性があること」や「自分で考え自分で動けること」がよく挙げられます。一方で、それが自分で考えたことであっても、「自分勝手」に動き始めると、組織としては困った状態になります。
新入社員に求められる「主体性」を正しく育むために、上司は具体的にどのような行動をとると良いでしょうか。それをGTD®で考えてみたいと思います。
教育研修プログラム「GTD® Getting Things Done® ストレスフリーの仕事術」は、次々と生じる「やるべきこと」をすばやく整理して、高い生産性を維持することを目指します。「把握する」「見極める」「整理する」「更新する」「選択する」という5つのステップから構成されています。全体像などは割愛しますが、新入社員の主体性を育むためには、5つのステップの最初の2つが役に立ちそうです。
1. 把握する
1つめは、身の回りにあるもので「気になること」や、心と頭の中にある「気になること」を《把握する》ステップです。
新入社員は、自分の所属する企業や業務について、ほとんどなにも知りません。「気になること」が頭の中にたくさんあるはずです。まずは、それをすべて書き出すよう促します。「気になること」が頭にある状態は、前向きな思考や積極的な行動を妨げて、主体性発揮の障害になります。
2. 見極める
2つめは、「気になること」を解決するための具体的な行動と、その目的を明確にする《見極める》ステップです。
新入社員は、業務について分からないことが多いため、解決のための行動を明確にしようとしても、まず何をすれば良いかの判断がつきません。ここでも、上司や先輩によるサポートが必要です。
具体的な行動を考えさせるときは、行動を起こすうえで重要な「最初の一歩」と、「目指すゴール」の2点を明確にするようガイドします。例えば、「○○という業務の勉強をしなくちゃ…」と考えたら、最初の一歩を明確にします。
この場合は、「今日、自宅へ戻る途中で書店に行き、○○について書かれた本を買う」といったレベルまで具体化します。最初の一歩があやふやでは、いつまでたっても行動を起こさない可能性があるからです。そして、「○○という業務を1人でこなす」といった形で、目指すゴールも明確にします。
気になることと目指すゴールの例
| ◎気になること | ○○業務の勉強 |
|---|---|
| ▽最初の一歩 | 帰りに書店で○○の本を買う |
| ▽目指すゴール | ○○業務を1人でこなす |
「行動」ではなく「自分の行動を考える」を身につける
実際に新入社員と《見極める》ステップを行うと、「これ、何の意味があるんですか?」と聞かれることがあります。彼らの視点では、行う必要や理由が分からないために出てくる疑問です。ここで、「いいから言われたことをやれよ!」と言いたくなる方は注意が必要です。こういった問いに向き合うことが、仕事を《見極める》ことのスタートです。
《見極める》ステップは、自分の現状を把握すること、そして目指す先を明確にすることでもあります。それが曖昧なまま、行動だけを「いいからやれ」で押しつけると、結果的に、自分で次の行動が考えられない「指示待ち人間」を作ります。
「主体的に動く」とは、精神論ではありません。今回ご紹介したように、自分の行動や、目指すべき先を明確にすることを習慣的に行うこと、またその精度を高めていくことであり、それこそが、新入社員に求められる主体性だと考えます。
目指すゴールを明確にすることは、より「正しい」具体的な行動につながります。「主体性を発揮して活躍する」という表現の実践イメージとして、ふさわしいものではないでしょうか。