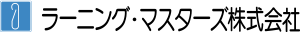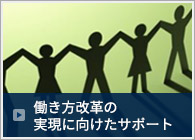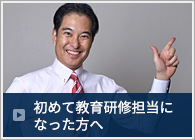オンライン企業研修の課題を考える 第1回
1年経って振り返るオンライン研修
 感染症対策などの理由から、企業研修のオンライン化が進み1年が経ちます。受講者も、事務局または講師として運営や実施をする皆さんも、それぞれ経験を重ねていることと思います。
感染症対策などの理由から、企業研修のオンライン化が進み1年が経ちます。受講者も、事務局または講師として運営や実施をする皆さんも、それぞれ経験を重ねていることと思います。
当社でも、昨年春から研修のほとんどがオンライン実施となり、試行錯誤の中で経験とノウハウが蓄積されてきました。そこで今回からシリーズとして、以下の項目に分け、当社講師陣から寄せられた情報をお伝えしていきます。
- オンライン研修を実施して感じる課題
- グループワークをするうえで注意する点
- 今後に向けての注意点、または期待すること
それぞれの項目を「講師・運営側」と「受講者側」の側面で分けて整理しています。寄せられた情報をできるだけそのままお伝えしていきますので、ぜひ今後の皆さまの人材育成にお役立てください。
シリーズ「オンライン企業研修の課題を考える」
- オンライン研修を実施して感じる課題
- 講師・運営側から見た受講環境(第1回)
- 運営、その他(第2回)
- 受講者の物理的な側面と心理面(第3回)
- グループワークをするうえで注意する点
- 今後に向けての注意点、または期待すること
1. オンライン研修を実施して感じる課題
(「講師・運営側」として)
対受講者、受講者の環境
当社講師陣から寄せられた情報
- 受講者の回線、使用する機器といった環境に大きく影響を受ける。通信トラブルなど、集合型の研修より突発的なアクシデントが発生する確率も高い。
- 講師の音声が途切れているなど、軽微なトラブルは、伝えてもらわないかぎり把握できない。そういったトラブルによる受講意欲の低減が起こりうる。
- 使用するツールの習熟度で進行に差が生じるので、事前の確認が必要。チャットで質問をすることに、いかに慣れてもらうかが重要。
- 受講者のカメラオフは、反応がつかめず、セミナーの雰囲気を作るのも難しい。
- グループワークなど、全体を把握することができない。また、対面よりも伝わる情報が減るため、理解度やワークの様子、他の受講生との関わりなど、つかめない部分が多い。一部の積極的な受講者の反応だけで「理解できている」「盛りあがっている」と判断してしまいがち。
- チャットや音声での発表は、どうしても敷居が高い。雑談のようなコミュニケーションが取りにくく、どこまで本音を引き出せているのかといったところが把握しかねる。
- 受講者に合わせた進行が難しい。講師が主体の、誰が受講生でも変わらないようなセミナーになってしまう。
- ハイブリッド型(対面とオンラインの複合型)の場合、教室にいる受講者に比べてオンラインの受講者への対応が間接的になり、不公平感が発生する可能性がある。
まずは、接続環境の安定が、講師にとっても受講者にとっても、最初にクリアしなければならない点と言えます。
また、講師としては、集合型の研修と比較して受講者の反応が少ない、つかみにくいことに苦労している様子がうかがえます。情報の不足をどう補うかが鍵といえます。そのためには、使用するオンラインツールの機能を活用する、また活用できるように受講者をどう巻き込むかがポイントです。
ハイブリッド型は、実施側からすれば、離れた拠点などからも参加させたいという思いからのものですが、講師にとっては、新たな課題を投げかけているようです。
次回は「オンライン研修を実施して感じる課題」から講師・運営側の後半、「運営・その他」をお伝えします。
おすすめのページ
おすすめの教育研修プログラム
おすすめのコラム
オンライン企業研修の課題を考える(全7回)